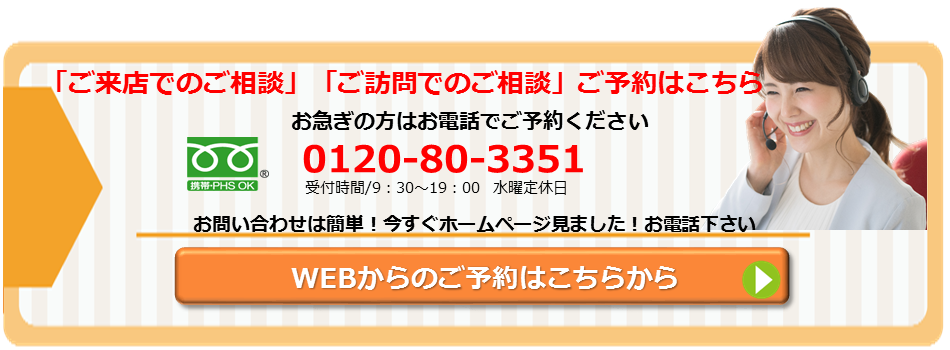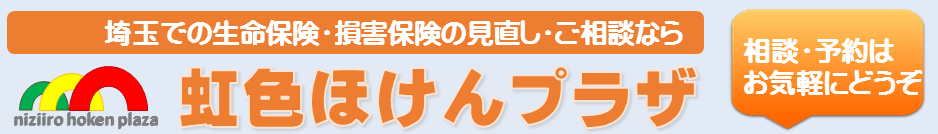私立幼稚園に3歳から入園し、小学校、中学校、高等学校が公立、大学が私立の文系に進んだとすると約1,300万円の教育資金が必要になります。
(日本政策金融公庫 平成27年教育の負担実態調査より抜粋)
子どもが2人に場合は単純に倍の金額が必要となります。
(子どもにかかる教育資金についてはこちら)
大黒柱である人に万が一があった場合、残された配偶者には、この負担が重くのしかかってきます。また子どもに不自由な思いをさせることなく育て上げるためにも死亡保障の増額や追加加入による保険の見直しは必要となります。増額や追加加入する死亡保障を検討する際には、必要保障額の計算が必要になってきます。
〇「ライフステージごとの必要保障額の推移」
以下の図は必要保障額の推移を表したものです。
「就職」→「結婚」→「子どもの誕生」→「子どもの独立」→「セカンドライフ」の順に進んでいきますが、やはり「子どもの誕生時」が必要保障額のピーク時になります。
子どもが独立後は、自分のため、夫婦2人ための生活に移っていきますので、大きな保障は不要となります。

〇 必要保障額を確認する
子どもが18歳になるまでは公的な保障で「遺族基礎年金」が給付されます。社会保障も準備されているので、残された遺族が生活していくにはどれ位の資金が必要なのか、必要保障額をきちんと算出し、死亡保障の金額を考えていきましょう。
〇 死亡保障見直し例
見直し例で多いのが「掛捨てタイプの定期保険」や「収入保障保険等」での保障の準備です。
定期保険や収入保障保険を活用することによって、比較的安価に大きな保障を準備することができます。全く死亡保険に加入していない場合には、必要保障額を算出しあらたに加入していきましょう。
現在、死亡保険に加入している場合には、どれくらい保障が足りないか計算し、不足分を追加で増額するか、特約で定期保険特約がセットされている場合は、特約部分を解約し、収入保障保険をあらたに新規加入していく方法もあります。
特約の解約にあたっては、あらたな保険料の金額や解約のリスクをしっかり確認したうえで行っていきましょう。